AIでなくならない仕事
Day15:宗教者・哲学者 ― 生き方や意味を問う仕事
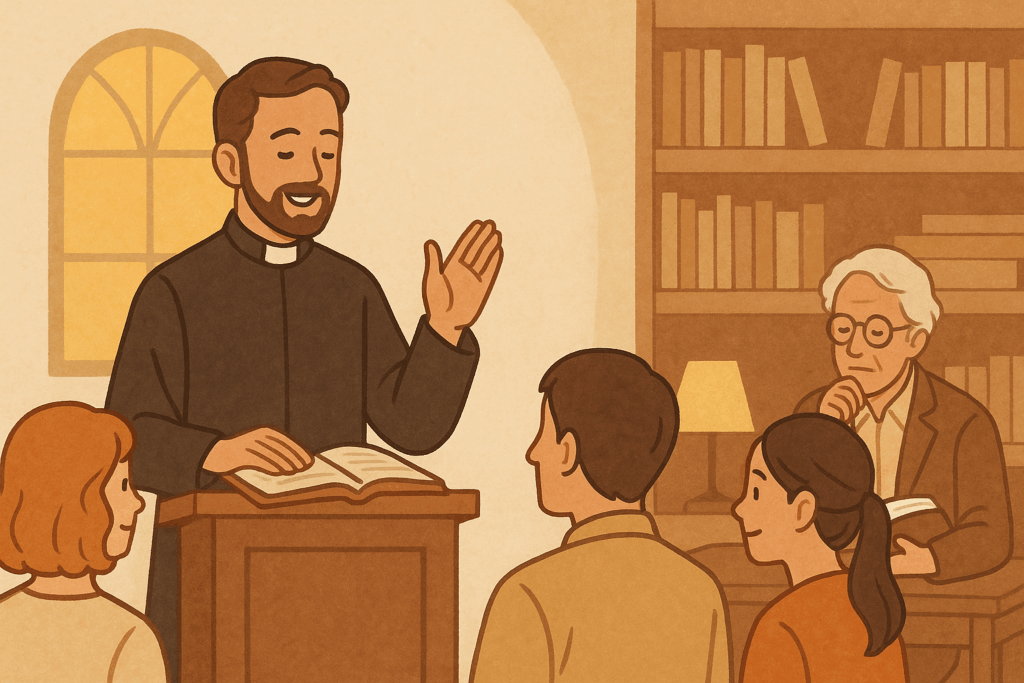
はじめに
AIは高度なデータ処理や情報検索において人間を凌駕しています。しかし、「人はなぜ生きるのか」「人生の意味とは何か」といった根源的な問いには、明確な答えを出すことはできません。宗教者や哲学者は、こうした抽象的かつ人間的な問いに向き合い、人々に指針や安心を与える存在です。この役割は、AIがいくら進化しても代替できない領域です。
AIが苦手とする「意味の探求」
AIはデータからパターンを導くことは得意ですが、「なぜそれが大切なのか」といった価値判断には対応できません。宗教や哲学は、人類の歴史の中で培われてきた知恵や文化的背景に根ざしており、個人の感情や社会全体の文脈と深く結びついています。これを単なる数値やアルゴリズムに置き換えることは不可能です。
宗教者・哲学者の役割
- 人生に意味を与える
苦しみや逆境の中で「なぜ生きるのか」という問いに答えを模索する。 - 共同体の精神的支柱となる
宗教的儀式や哲学的対話を通じて、人々をつなげる。 - 倫理や価値観を提示する
科学や経済の合理性だけでは判断できない問題に対し、人間的な視点から方向性を示す。 - 安心を提供する
不安や死に対する恐れに寄り添い、心の拠り所となる。
これらの役割は、データ処理ではなく「人間の経験」と「文化的背景」に基づいているため、AIが代替することはできません。
哲学・宗教が必要とされる場面
- 社会の変化に直面するとき:AIやテクノロジーの進化に伴う倫理問題。
- 個人が人生の岐路に立つとき:病気や死別、転機に伴う問い。
- 共同体の結束が求められるとき:災害や社会不安に対する心の支え。
こうした場面で必要なのは「人間同士の対話」と「共に考える姿勢」です。
まとめ
宗教者や哲学者は、人間が避けられない「生き方の問い」に応える存在です。AIがいくら進化しても、人々に安心や意味を与える役割は人間にしか果たせません。だからこそ、この仕事はAI時代にもなくならないどころか、むしろ重要性が高まると言えるでしょう。
次回は「Day16:アーティスト ― 個人の感性が生む価値」を取り上げます。
出典
- Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning (Beacon Press, 2006)
- 哲学会編『哲学入門』(岩波書店, 2020年)

