色について学ぶ30日 ― 色を知ると世界がもっと楽しくなる
【Day2】三原色と色の混ぜ方 ― 赤・青・黄の魔法
私たちが日常で見ている色は、無数の色に見えても、実は 「わずか3色を混ぜるだけで」 作り出すことができます。
その3色とは、絵の具や印刷で使われる “色の三原色(赤・青・黄)”。
これらを組み合わせることで、ほぼすべての色を作ることができます。
「三原色」はただの色ではなく、色の仕組みを理解するための土台です。
Day2では、この三原色の基本と“色が混ざる魔法”をやさしく解説します。
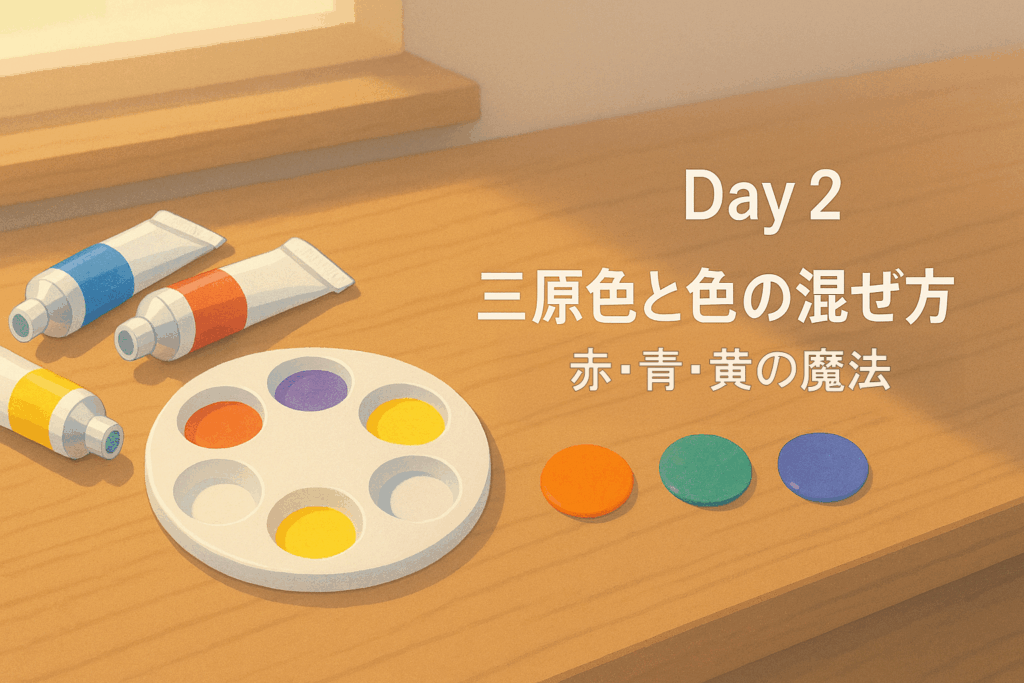
■ 色の三原色とは?(R・B・Y)
色の三原色とは、
・赤(Red)
・青(Blue)
・黄(Yellow)
の3色のことです。
この3つは、混ぜても他の色で代用できない「最も基本的な色」です。
- 赤 + 黄 = オレンジ
- 黄 + 青 = 緑
- 青 + 赤 = 紫
このように、三原色どうしを混ぜることで “中間色” が生まれます。
さらに、水の量や彩度(あざやかさ)を調整することで、無限のバリエーションに変化します。
■ 三原色を使うと「世界中の色」が作れる理由
三原色のすごいところは、「色相(色み)」を滑らかにつなぐことができる点です。
赤 → オレンジ → 黄 → 緑 → 青 → 紫 → 赤
という、色相環(カラーホイール)を描いたとき、
三原色を起点にすべての色が“循環”していきます。
つまり、
三原色を軸にすべての色が生まれる
という考え方が色彩学の基本なのです。
■ “混ぜ方”で変わる色の性格
色はただ混ぜるだけでなく、配分によって表情が大きく変わります。
● 1:1で混ぜると「純粋な中間色」
- 赤+青=紫
- 黄+青=緑
など、誰が作ってもほぼ同じ色味に近づきます。
● 赤を多めにすると「赤みのある紫」
● 黄を多めにすると「黄みの強い緑」
…など、配分で印象がまったく変化します。
絵を描く方やデザイナーが色を作るとき、
「赤 2:青 1」などのように、配分を感覚で覚えていきます。
■ 三原色×白・黒で広がる世界
三原色に 白(明るくする色) を混ぜるとパステル調に、
黒(暗くする色) を混ぜると落ち着いた深い色になります。
- 白を足す → 明度UP、ふんわり柔らかい印象
- 黒を足す → 明度DOWN、落ち着き・上品・重厚感
これにより、三原色から生まれる色のバリエーションは何百、何千にも広がります。
■ 絵の具と光の「三原色の違い」
実は三原色には2種類あります。
- 物体(絵の具・インク)の三原色:赤・青・黄
- 光の三原色:赤・緑・青(RGB)
スマホやテレビの画面が RGBで色を作る方式 なのに対し、
絵の具は「絵の具同士を“混ぜて”色を作る方式」。
Day2ではまず“絵の具の三原色”から理解していただければ十分です。
光の三原色は Day3・Day4 で詳しく解説します。
▼ まとめ
- 三原色は「赤・青・黄」
- 三原色を組み合わせることでほぼ全ての色が作れる
- 配分で色の性格が変わる
- 白や黒を混ぜると明度と雰囲気が大きく変わる
- 絵の具の三原色と光の三原色は別もの
三原色は色の世界の“出発点”。
ここを理解することで、これから学ぶ色の法則が一気にわかりやすくなります。
▼ 出典・参考
- 日本色彩学会『色彩の基本』
- Bauhaus 色相論 資料
- Adobe Color / カラーホイール

