80年代歌謡曲について
Day15:バブル経済とディスコソング ― 荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー」
1980年代後半、日本はまさに バブル経済の絶頂期 を迎えていました。街にはブランドショップやディスコが立ち並び、夜ごとに若者たちが煌びやかな衣装をまとって集い、朝まで踊り明かす――そんな光景が当たり前のように広がっていたのです。音楽はこの熱狂の中心にあり、その象徴が荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」でした。
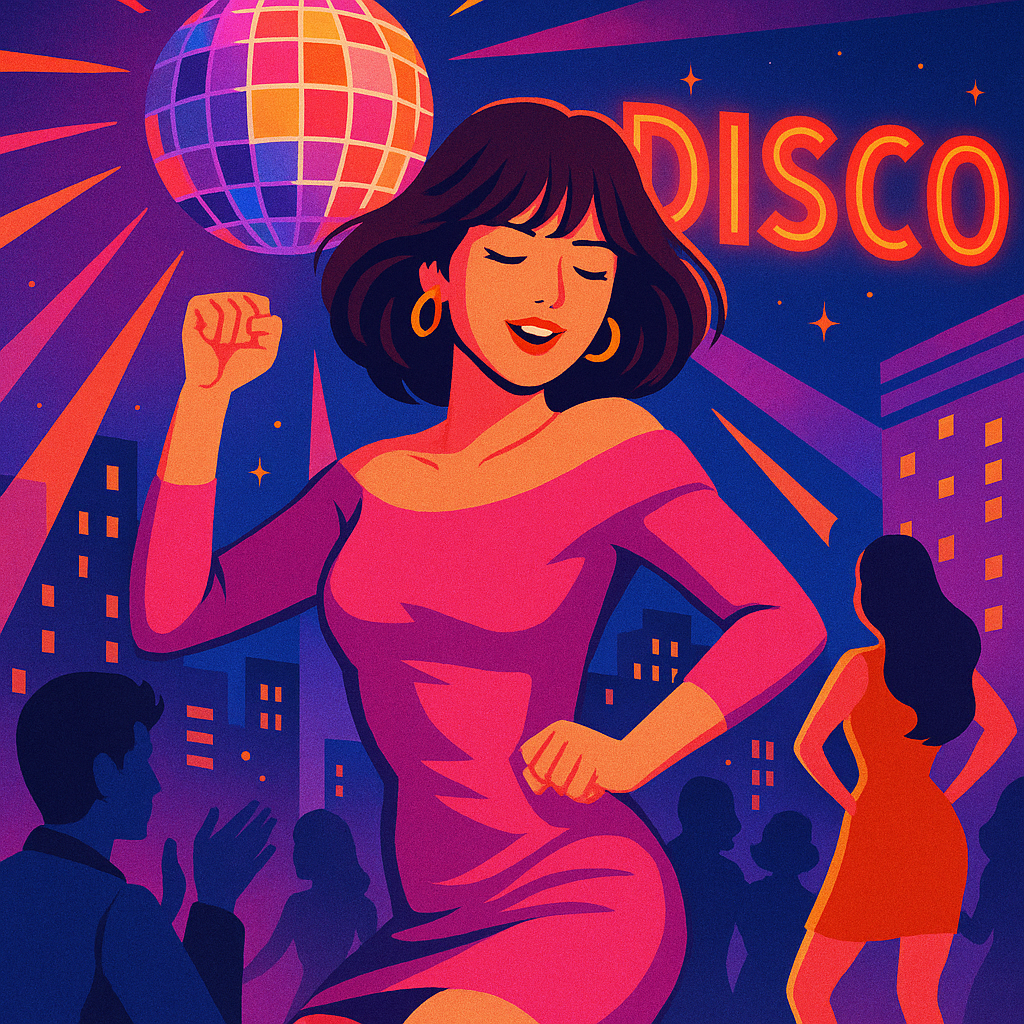
「Eat You Up」から「ダンシング・ヒーロー」へ
「ダンシング・ヒーロー」は、イギリスの歌手アンジー・ゴールドが1985年に発表した「Eat You Up」のカバー曲です。日本語詞を付けてリリースされた同曲は、オリジナルのエネルギッシュなダンスビートを活かしつつ、日本の歌謡曲らしいキャッチーさを加えたことで一躍大ヒットとなりました。
荻野目洋子自身の小柄でキュートなビジュアルと、キレのあるダンスパフォーマンスは、バブル時代のディスコシーンにぴったりはまりました。特に、ミラーボールの下で繰り広げられるダンスとこの楽曲のリズムが重なり合うことで、まさに「時代のサウンドトラック」となっていったのです。
バブル文化と「ワンレン・ボディコン」
バブル経済を語る上で欠かせないのが、「ワンレン・ボディコン」と呼ばれる女性たちのファッションです。ロングヘアをワンレングスに切り揃え、体にフィットした派手なボディコンシャス・ドレスを着こなし、ディスコで踊る姿は当時の象徴そのものでした。
「ダンシング・ヒーロー」は、まさにこの文化と強固に結びつきました。ディスコでは荻野目の楽曲が流れると、女性たちはこぞってダンスフロアに飛び出し、男性たちはその姿に熱狂しました。音楽が単なる娯楽ではなく、 ライフスタイルや社会現象と直結していた ことを示す好例といえるでしょう。
ディスコという社交場
バブル期のディスコは、単なる遊びの場ではなく、仕事や恋愛の出会いの場としても機能していました。煌びやかな照明と大音量の音楽に包まれながら、企業戦士やOLたちが日常を忘れて踊り、語らい、恋愛へと発展する――。その場の空気感を凝縮した存在が「ダンシング・ヒーロー」であり、当時の若者たちにとっては「自分たちのアンセム」ともいえる曲でした。
社会現象からリバイバルへ
1985年のリリースから30年以上経った2017年、この曲は再び注目を浴びました。大阪府立登美丘高校ダンス部が「バブリーダンス」と銘打ったパフォーマンスで「ダンシング・ヒーロー」を採用し、YouTubeやテレビ番組で大きな話題を呼んだのです。
肩パッド入りのボディコンスーツをまとい、バブル期を彷彿とさせる振り付けを見せる女子高生たちの姿は、80年代を知らない世代にも強烈なインパクトを与えました。その結果、「ダンシング・ヒーロー」はオリコンのデジタルランキングで再浮上し、昭和と平成をつなぐ「時代を超えた名曲」として再評価されました。
音楽的な魅力
「ダンシング・ヒーロー」の音楽的な魅力は、やはり キャッチーなサビとリズム感 にあります。一度聴けば忘れられないフレーズが繰り返され、自然と体が動き出す――これこそダンスミュージックの真骨頂です。
さらに、カバー曲でありながら日本語詞によって「青春」「恋愛」といった普遍的なテーマが歌われたことで、幅広い層に共感を呼びました。日本独自のアレンジ力が、洋楽のビートを歌謡曲として昇華させたといえるでしょう。
まとめ ― 「ダンシング・ヒーロー」が映した時代
荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」は、単なるヒット曲ではなく、バブル経済という時代の空気を凝縮した存在でした。ディスコ、ファッション、ライフスタイル――そのすべてがこの曲を通じて結びつき、日本の大衆文化の一つの頂点を築いたのです。
そしてリバイバルを経てわかったことは、この楽曲が「一時代の懐メロ」ではなく、世代を超えて踊り継がれる 普遍的なダンスアンセム であるということです。バブルの熱狂を知らない若者が楽しむ姿は、「音楽の力が時代を越える」ことを改めて証明してくれました。
参考文献
- 馬飼野元宏『バブル時代のポップカルチャー』シンコーミュージック、2018年
- 渡邊裕子『昭和アイドル歌謡史』青弓社、2020年
- 朝日新聞「バブリーダンスが呼んだ『ダンシング・ヒーロー』再ブーム」2017年記事
- 読売新聞「ディスコとバブルの光と影」2019年記事
- NHK『映像の世紀バブル篇』2021年放送
