80年代歌謡曲について
Day28:80年代後半から90年代への移行 ― J-POPの胎動
1980年代の歌謡曲は、その華やかさと多様性によって日本の音楽文化を大きく彩りました。しかし時代が進むにつれ、音楽シーンには新しい変化の兆しが訪れます。80年代後半から90年代への移行期にかけて、日本の音楽は「歌謡曲」から「J-POP」へと進化し始めました。その象徴的存在が TM NETWORK や B’z などのアーティストであり、同時にアイドル像の変容もこの時期に重なります。
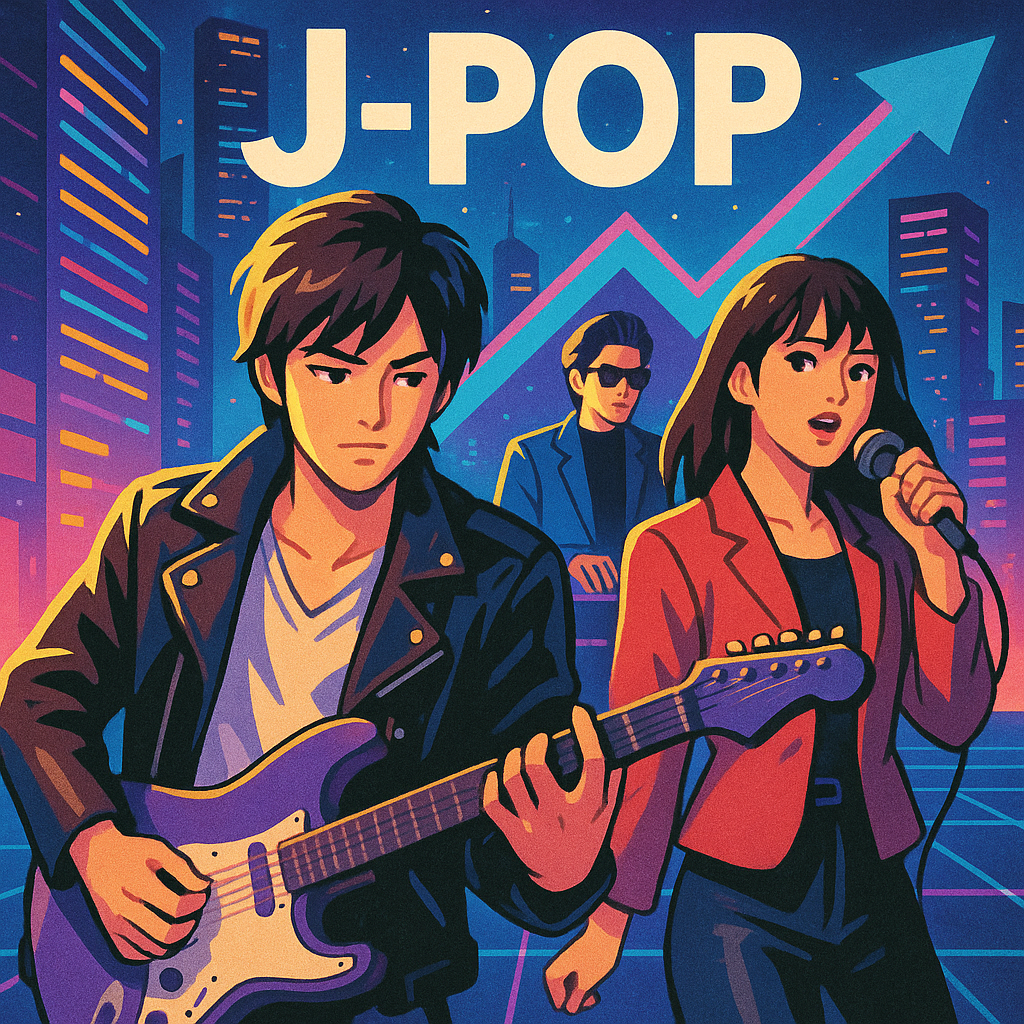
TM NETWORKと近未来的サウンド
1987年、アニメ『シティーハンター』のエンディングテーマに起用された TM NETWORK「Get Wild」 は、従来の歌謡曲とは一線を画する革新的な楽曲でした。シンセサイザーを駆使した近未来的なサウンド、都会的でクールなイメージ、そしてアニメとのタイアップ効果によって、若者の心をつかみました。
小室哲哉を中心とするTM NETWORKは、デジタルサウンドとポップメロディを融合させ、日本の音楽が新しい時代へ進むことを鮮やかに示しました。後に小室が安室奈美恵やglobe、trfを手がける「小室ファミリー」へとつながる流れを考えると、この時期のTM NETWORKの役割は非常に大きかったといえるでしょう。
B’zの登場とロック色の強化
1988年にデビューした B’z も、この時期の音楽シーンを語る上で欠かせません。松本孝弘のギターと稲葉浩志のパワフルなボーカルが生み出すロックサウンドは、歌謡曲の延長線上にありながらも明確に異なるエネルギーを持っていました。
「BAD COMMUNICATION」(1989年)でブレイクすると、B’zは一気に若者文化の中心に躍り出ます。歌謡曲的なメロディのキャッチーさを残しつつ、洋楽的なロックアプローチを取り入れた彼らの音楽は、まさにJ-POPへの架け橋でした。
変化するアイドル像
アイドル文化も80年代後半には大きな変化を見せました。従来の「清純派」や「可憐なイメージ」に加えて、 工藤静香 や 中山美穂 のように「アーティスト性」や「都会的な大人の女性像」を打ち出す存在が登場しました。
工藤静香はアイドル出身でありながら、独特のハスキーボイスと大人びた歌詞で本格的なアーティストへと進化。中山美穂は歌手活動と並行して「トレンディドラマ」の主演女優としても活躍し、音楽と映像を融合させた総合的なスター像を築き上げました。
この流れは1990年代の安室奈美恵、小室ファミリー、さらには浜崎あゆみなど、「自らを表現するアーティスト型アイドル」への道を切り開いたといえるでしょう。
「歌謡曲」から「J-POP」へ
1989年には、音楽雑誌『JAPAN』などの影響もあり、従来の「歌謡曲」という言葉から「J-POP」という呼び方へと移行する流れが強まりました。歌謡曲がテレビや歌番組中心の大衆的な響きを持っていたのに対し、「J-POP」という言葉は、より広く、洋楽的で洗練されたポップミュージックを指すイメージがありました。
この時期は、ちょうどバブル経済の絶頂期から崩壊へと向かう転換点でもありました。社会の空気の変化とともに、音楽もまた「楽しさ一辺倒」から「個性や自己表現の重視」へとシフトしていったのです。
過渡期としての80年代後半
80年代後半は「歌謡曲の最盛期」であると同時に、「J-POPの胎動期」でもありました。シンセサイザーを駆使したデジタルサウンド、ロック色の強化、アイドルの自己表現化、そしてメディア戦略の進化。これらすべてが重なり合い、90年代の日本音楽シーンを支える基盤が築かれました。
結果として、90年代にはミリオンセラーが続出し、日本の音楽産業は世界的にも稀に見る大成功を収めることになります。その原点を探ると、やはり80年代後半の過渡期に行き着くのです。
まとめ
1980年代後半は、歌謡曲が黄金期を迎えながらも、新しい時代=J-POPへの橋渡しを果たした時代でした。TM NETWORKの未来的サウンド、B’zのロック的エネルギー、そして工藤静香や中山美穂の自己表現型アイドル像。これらが織りなす多彩な動きこそが「J-POPの胎動」だったといえるでしょう。
華やかな歌謡曲文化が次の時代へとバトンを渡したこの瞬間を振り返ると、日本の音楽史の転換点に立ち会っていたことがよくわかります。
参考文献
- 中川右介『歌謡曲の時代』新潮文庫、2006年
- 馬飼野元宏『80年代音楽の光と影』音楽之友社、2011年
- 音楽ナタリー「TM NETWORKとシティーハンター」特集
- 『読売新聞』「B’zブレイクと若者文化」(1989年)
- NHK BSプレミアム「J-POP誕生の瞬間」特集(2015年)
