謎バズ30
Day21:なぜSNSは中毒性があるのか?
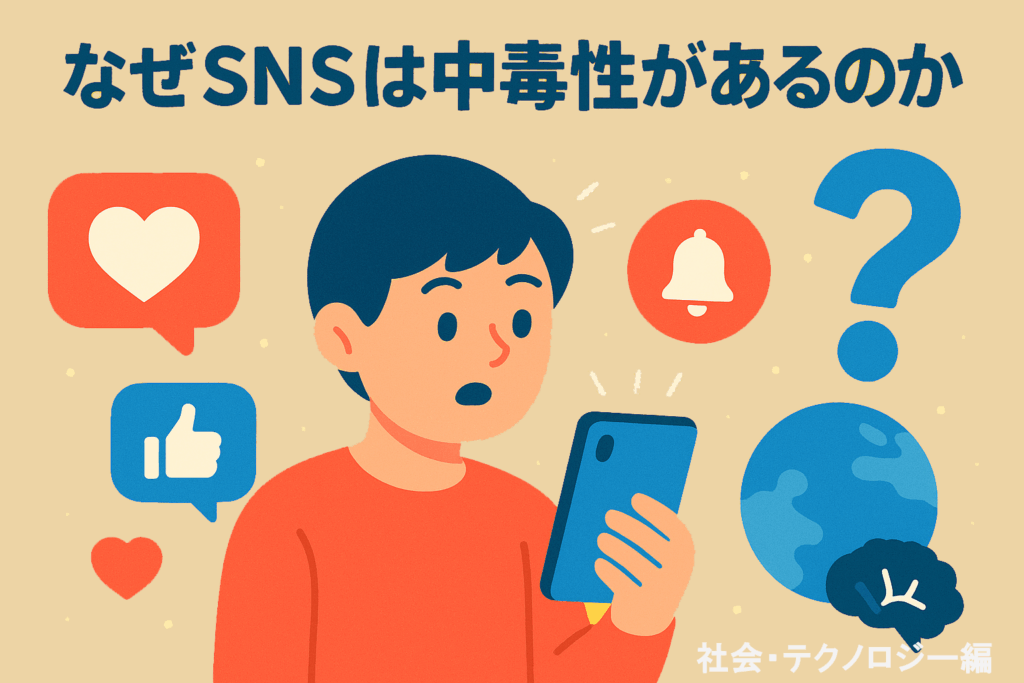
スマートフォンを手放せない、気づけばSNSを何時間も見てしまう。
現代人の多くが抱えるこの現象には、明確な科学的背景があります。
SNSは「ドーパミン中毒」を引き起こす設計になっています。
いいね!やコメント、シェアといったフィードバックは、脳内で快感物質ドーパミンを分泌させます。
この仕組みはギャンブルの報酬系と似ており、ランダムに報酬が得られることでさらに中毒性が増すのです。
また、SNSは「社会的承認欲求」を満たす場でもあります。
自分の投稿が評価されると「他者に受け入れられた」という安心感を得られます。
逆に反応が少ないと不安や焦燥感に繋がり、再び投稿や閲覧に依存するサイクルが生まれます。
さらに、情報が無限に流れてくるタイムラインは「取り残される恐怖(FOMO)」を刺激します。
これが「つい見てしまう」習慣を強化するのです。
まとめ
SNSの中毒性は「ドーパミン報酬系」「承認欲求」「FOMO」が組み合わさった結果。
人類の心理を巧みに利用した設計が依存を生む。
📖 出典・参考文献
- Alter, A. (2017).
Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked.
Penguin Press.
→ SNSやアプリが「やめられない」仕組みを心理学・脳科学から解説した書籍。 - Meshi, D., Tamir, D. I., & Heekeren, H. R. (2015).
The emerging neuroscience of social media.
Trends in Cognitive Sciences, 19(12), 771–782.
→ SNS利用と脳の報酬系(ドーパミン分泌)の関連を解説。 - Andreassen, C. S., et al. (2012).
The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem.
Personality and Individual Differences, 52(4), 447–451.
→ SNS依存傾向と承認欲求・自己愛・自尊心の関係を分析。 - Montag, C., & Walla, P. (2016).
Carrying the Internet in your pocket: Smartphone and the emergence of a new social behavior.
Computers in Human Behavior, 62, 621–627.
→ スマートフォンとSNSの常時接続が人間の行動に与える影響を調査。 - 日本厚生労働省・国立精神・神経医療研究センター
→ SNS依存の問題とメンタルヘルスへの影響に関する国内研究。
✅ 補足
- SNSの中毒性は
- 脳の報酬系(ドーパミン回路)
- 承認欲求(いいね・フォロワー)
- アルゴリズムによる最適化された刺激
によって強化される。

