最初は謎だよね!よく聞くビジネス用語
Day15:ロジカルシンキング ― 筋道立てて考える思考法
「ロジカルシンキング(Logical Thinking)」という言葉は、ビジネス書や研修でよく登場します。
「論理的に考えましょう」と言われても、実際には「どうすれば論理的になるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ロジカルシンキングとは、物事を筋道立てて整理し、矛盾のない形で結論を導く思考法です。
感情や思い込みではなく、「なぜそう言えるのか?」を明確にして考えるのがポイント。
この思考力は、プレゼン・報告・問題解決など、あらゆる場面で求められるビジネススキルです。
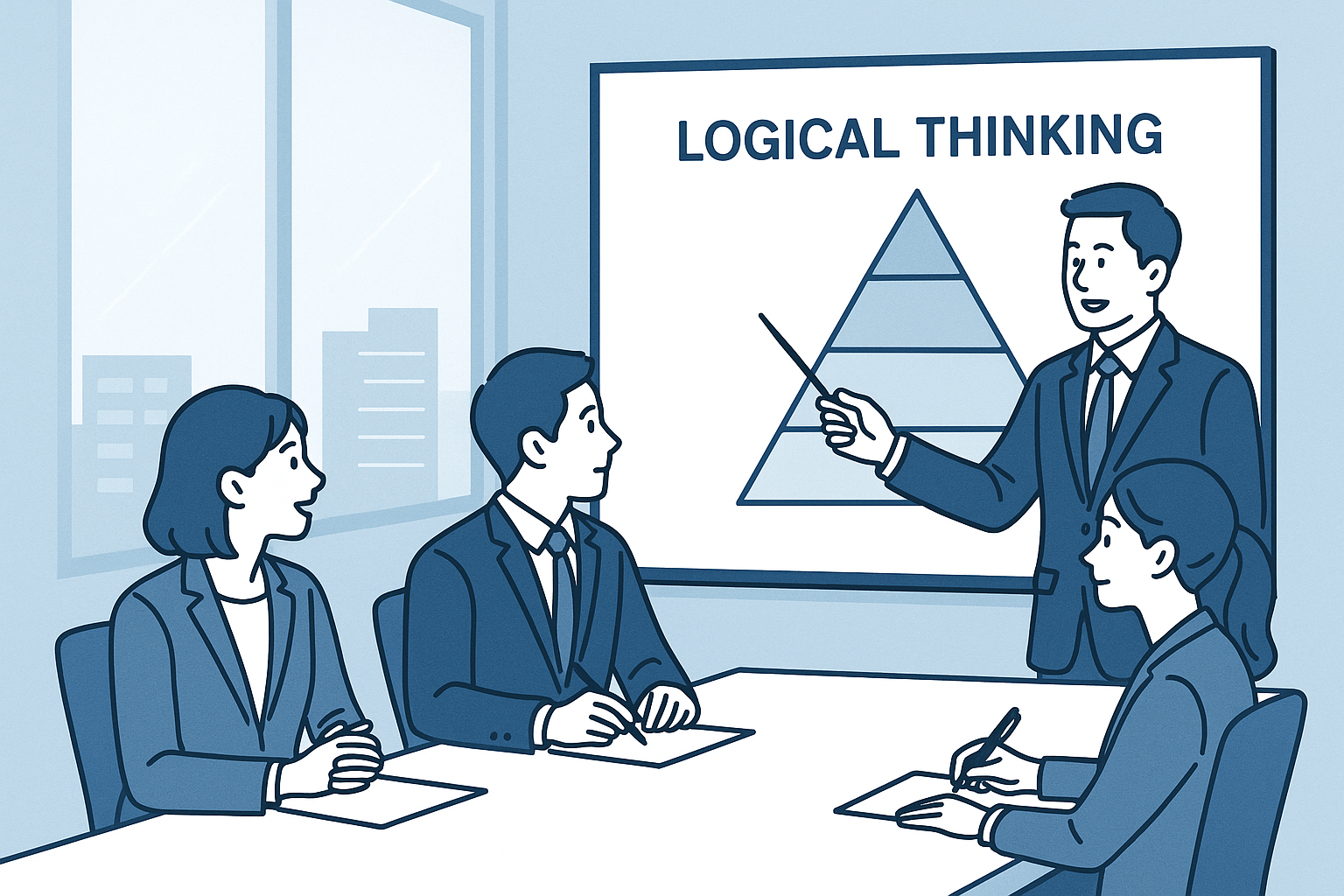
🔹 ロジカルシンキングの基本構造
ロジカルシンキングは、大きく分けて3つの要素で構成されます。
- 事実(Fact)
感情や推測ではなく、客観的なデータ・証拠に基づく。 - 根拠(Reason)
「なぜそう言えるのか」を説明する理由。 - 結論(Conclusion)
筋道に沿って導き出された答え。
つまり、
「なぜ?」→「だからこう考える」→「結果としてこうなる」
という一貫した流れを作ることがロジカルシンキングの基本です。
🔹 よくある「非ロジカル」な例
たとえば次のような会話を考えてみましょう。
Aさん:「この企画、やめた方がいいと思う。」
Bさん:「なんで?」
Aさん:「なんとなくうまくいかなそうだから。」
これは「感情ベース」の典型例です。
一方で、ロジカルに言い換えるとこうなります。
「過去3回の同様の施策では、費用対効果が平均30%低かったため、今回は別の手段を検討したい。」
このように「データ」+「理由」+「結論」がそろえば、説得力が格段に高まります。
🔹 ロジカルシンキングの代表的手法
- MECE(ミーシー)
「漏れなく・ダブりなく(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)」情報を整理する考え方。
例:「売上が下がった理由」を、商品・価格・販路・顧客の4視点で整理する。 - ピラミッド構造
結論を頂点に置き、下層に理由や事実を支える構造。
例:プレゼン資料を「結論→理由→具体例→補足」でまとめる。 - ロジックツリー
問題を枝分かれさせて要因を掘り下げる図解法。
例:「売上が下がった」→「客数減少」「単価低下」「リピート率低下」など。
これらのフレームワークを活用すると、思考の整理が一気にスムーズになります。
🔹 現場での使われ方
ビジネスの現場では、次のような場面で「ロジカルシンキング」が求められます。
- 上司への報告:「結論から先に」「理由を明確に」伝える。
- 会議での意見交換:「感情ではなくデータに基づく」議論をする。
- 問題解決:「根本原因を分解して特定」する。
ロジカルシンキングは、人を納得させるための技術でもあります。
「わかりやすく」「一貫性のある」説明は、それだけで信頼を生みます。
🔹 まとめ
ロジカルシンキングとは、筋道を立てて考え、説得力ある結論を導く思考法。
単なる分析力ではなく、「どうすれば相手に伝わるか」という構造的な考え方です。
感情的になりがちな会話も、「なぜそう思うのか」を整理するだけで、建設的な議論に変わります。
ビジネスで成果を出す人ほど、感情ではなく“論理”で人を動かしています。
📚 出典
- 日本能率協会『ロジカルシンキング入門』
- 経済産業省「ビジネススキル標準(ロジカルシンキング編)」
- Harvard Business Review “Developing Logical Thinking in the Workplace”
