AIでなくならない仕事
Day3:人間の強み① 感情と共感力
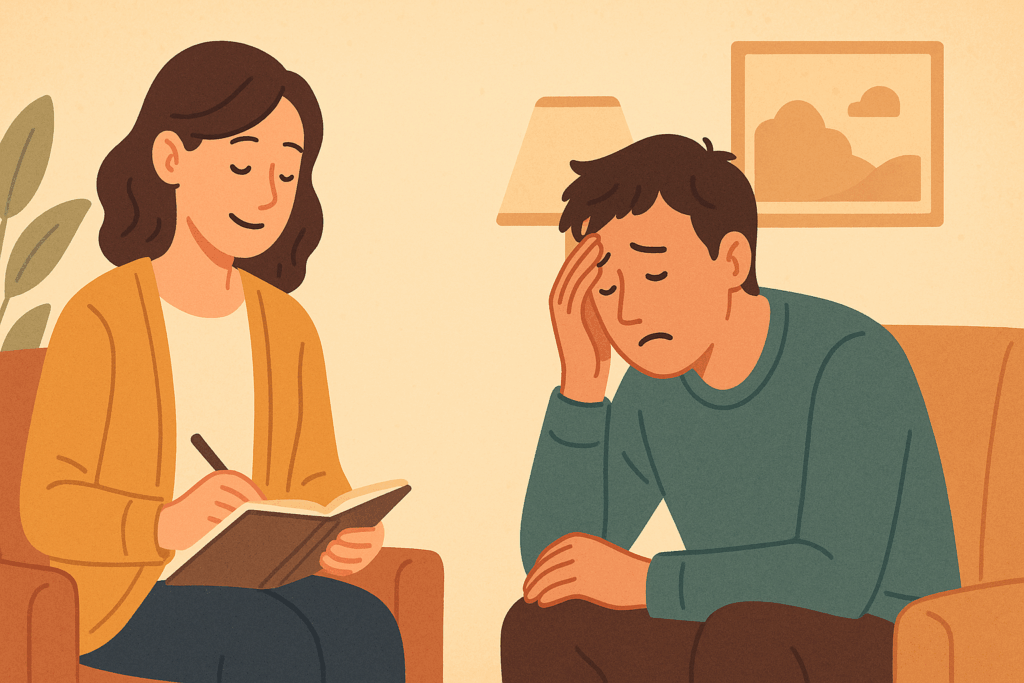
はじめに
AIは大量のデータを処理し、瞬時に答えを導き出すことができます。しかし、AIが苦手とする分野のひとつが「感情」と「共感」です。人と人との関係を築くうえで、この力は欠かせない要素であり、AI時代にこそ人間の強みとして際立つ部分です。
なぜ共感力が重要なのか
私たちは、日常生活の中で「この人は自分を理解してくれている」と感じたときに安心感を得ます。仕事においても、顧客対応や相談業務、教育の場などでは「相手の気持ちを察し、共感する」ことが信頼関係を築く基盤となります。
例えば、心理カウンセリングでは相談者の言葉の奥にある感情を読み取り、「大変でしたね」「その気持ちは自然ですよ」と受け止めることが求められます。AIも文章解析によって「ネガティブ」「ポジティブ」といった判断はできますが、本当の意味で「心に寄り添う」ことはまだ難しいのです。
共感力が活きる仕事の例
- カウンセラー・セラピスト
相手の感情を受け止め、安心感を与える専門職。 - 看護師・介護士
医療的な処置だけでなく、患者や利用者の不安を和らげる寄り添いが重要。 - 教師・保育士
子どもの小さな変化に気づき、励ましたり支えたりする力。 - 接客・販売職
単に商品を売るのではなく、相手の気持ちに合わせた提案が求められる。
これらの仕事は「人の感情」に密接に関わるため、AIが完全に代替することは困難です。
共感力を鍛えるには
共感力は生まれ持った資質だけでなく、訓練によって伸ばすことができます。たとえば、
- 相手の表情や声色に注目する習慣
- 相手の立場に立って考える練習
- 自分の感情を言葉にする習慣
これらを積み重ねることで、相手の心をより深く理解できるようになります。AI時代には「共感力が高い人材=代替されにくい人材」となり、キャリアにおいて大きな価値を持つのです。
まとめ
感情や共感は、人間関係を築くうえで不可欠な力です。AIが効率的に業務を進める一方で、人間が担うべきは「相手に安心感を与え、心に寄り添う」役割です。AI時代だからこそ、共感力を磨くことがこれからのキャリア戦略につながります。
明日は「創造性とオリジナリティ」について掘り下げていきましょう。
出典
- Carl R. Rogers, On Becoming a Person (Houghton Mifflin, 1961)
- 厚生労働省「心理職の専門性と今後の役割に関する検討会報告書」(2020年)

