ユーザー心理から見る広告作成術
Day4:認知バイアスと広告
広告やマーケティングにおいて、人間は「合理的に判断している」と思いがちですが、実際にはそうではありません。心理学や行動経済学の研究によれば、私たちの意思決定の多くは「無意識の偏り」に影響されています。これを 認知バイアス(Cognitive Bias) と呼びます。広告は、この認知バイアスを理解し、適切に活用することで大きな効果を発揮するのです。
アンカリング効果:最初の数字が基準になる
「通常価格9,800円 → 特別価格4,800円」という広告を見たとき、多くの人は「お得だ」と感じます。これは、最初に提示された9,800円が基準(アンカー)となり、それより低い価格が強く魅力的に見えるからです。この効果を使えば、値引きやセールの訴求力を高められます。
ただし注意したいのは、根拠のない「定価表示」や過度な割引は、消費者庁から不当表示とみなされる可能性がある点です。信頼を維持するには、事実に基づいた正しい価格設定が不可欠です。
フレーミング効果:見せ方で印象が変わる
「成功率90%」と「失敗率10%」は、数値的には同じ意味を持ちます。しかし、人はポジティブに聞こえる「成功率90%」に安心感を覚えやすいのです。広告においても、言葉のフレーミングによって印象は大きく変わります。
例えばダイエット広告で「3人に1人が効果を実感」と表現するより、「効果実感率70%」と表現した方が前向きに受け取られやすいでしょう。つまり「どのフレームで語るか」が広告コピーの鍵となるのです。
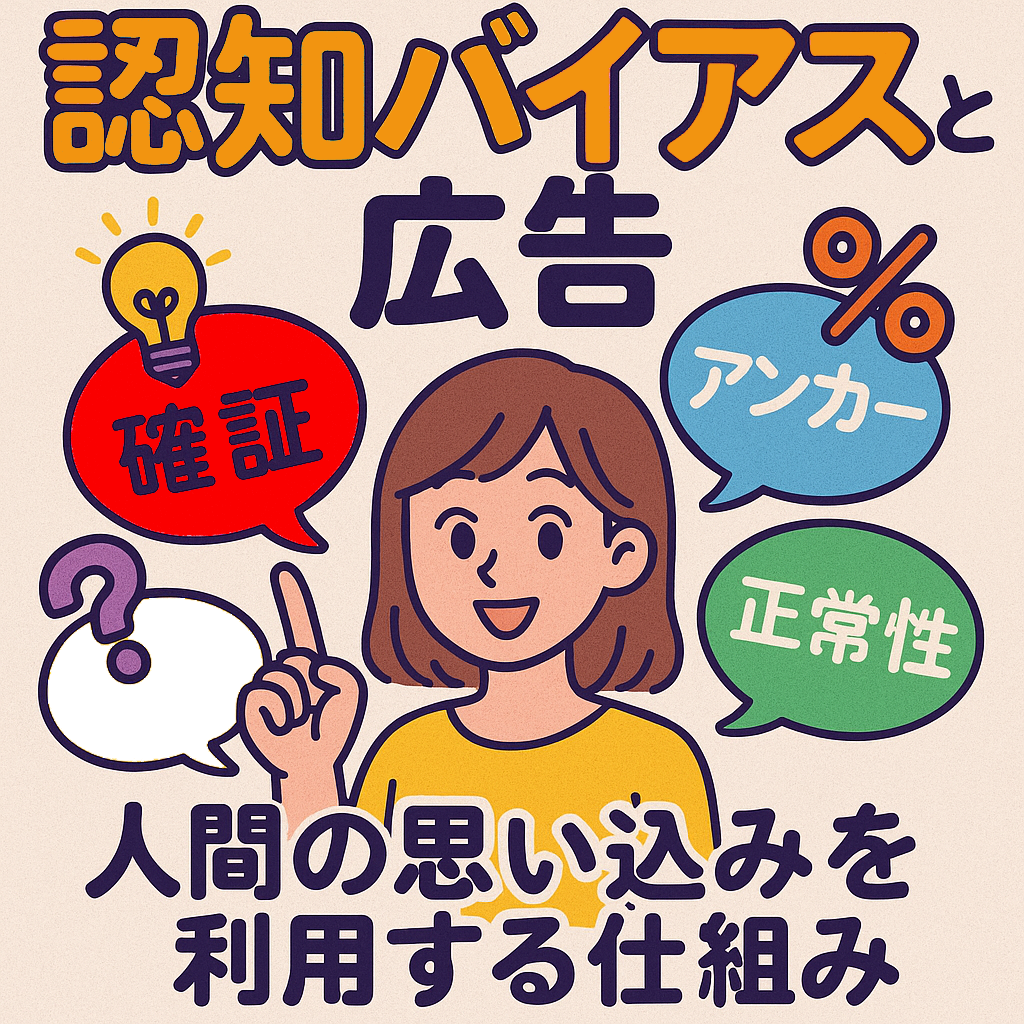
損失回避バイアス:人は損を嫌う
行動経済学の研究で有名な概念に「損失回避」があります。人は利益を得る喜びよりも、損を避けたいという心理を強く持っています。そのため広告で「今買えば得する」という訴求よりも「今買わなければ損をする」という表現の方が行動を促しやすい傾向があります。
典型的なのは「限定◯名」「本日限り」といった表現です。消費者に「今行動しないと損をする」という感覚を与え、購買を後押しする効果があります。
認知バイアス活用の注意点
認知バイアスを理解し、広告に取り入れることは非常に効果的ですが、誤用すると「人を誤導する広告」になりかねません。過剰な煽り文句や根拠のない訴求は、消費者の不信感を招き、企業ブランドを傷つける可能性があります。
重要なのは、 「人を騙すためではなく、価値を正しく伝えるために心理学を使う」 という姿勢です。実際の価値やメリットを、消費者が理解しやすい形で表現することが信頼につながります。
学びのポイント
- 人は合理的ではなく、心理的な偏りで意思決定をする
- アンカリング・フレーミング・損失回避などの認知バイアスを理解すると広告は強くなる
- 誤用は信頼を損なうため、倫理的に正しく活用することが重要
出典
- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.(行動経済学・認知バイアスの古典的研究)
- 消費者庁「不当表示に関する景品表示法」 https://www.caa.go.jp/
