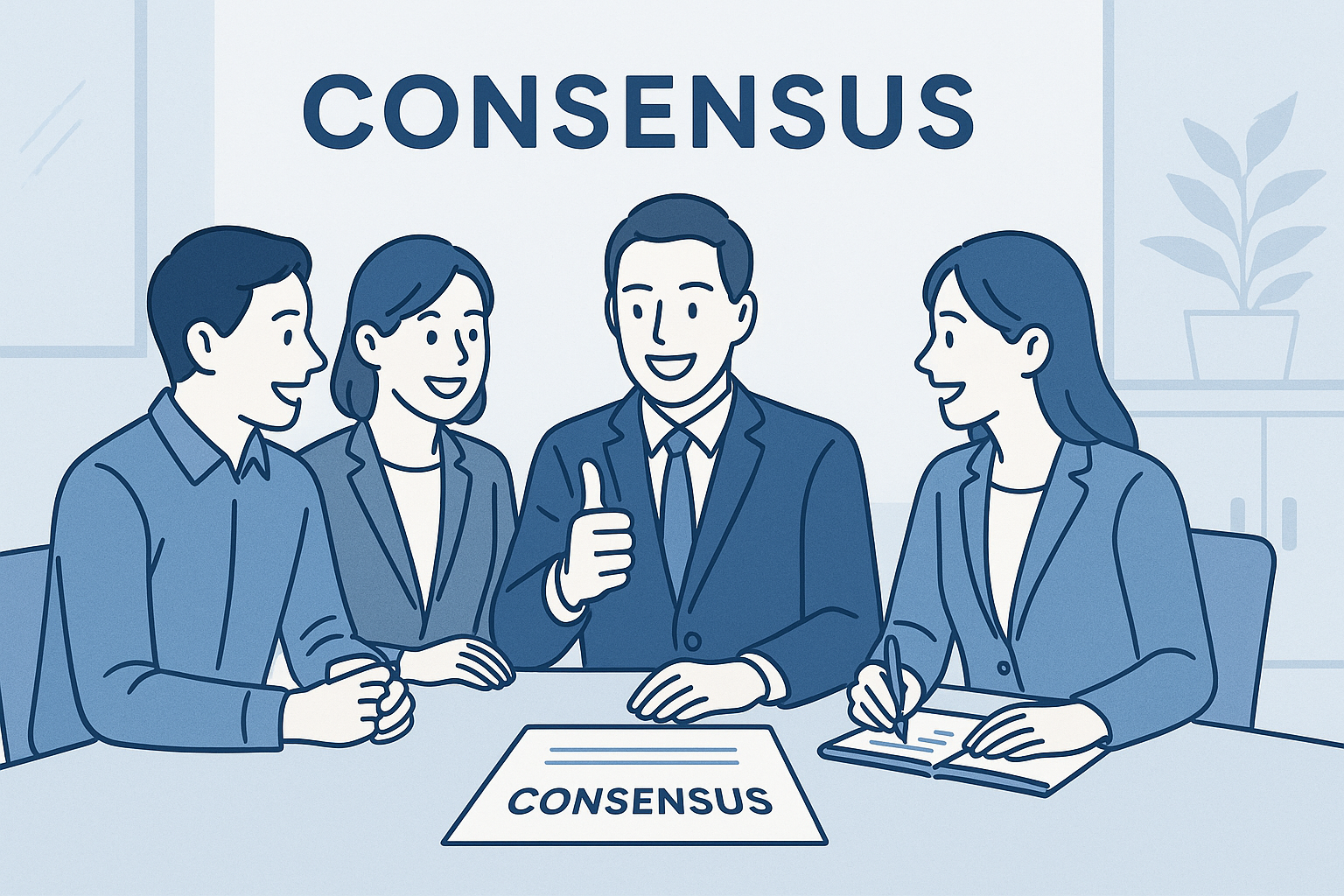最初は謎だよね!よく聞くビジネス用語
Day6:コンセンサス ― チームの合意をつくる力
「コンセンサス(Consensus)」という言葉を、会議やビジネスの場で耳にしたことがある人は多いでしょう。
しかし、「合意って“全員一致”のこと?」「多数決とどう違うの?」と疑問に思う方も少なくありません。
コンセンサスとは、チーム内で話し合いを重ね、全員が納得できる形で合意に至ることを意味します。
単なる「多数派の勝利」ではなく、「少数派の意見も尊重したうえでの合意形成」こそがポイントです。
語源はラテン語の consentire(共に感じる)で、“感情的にも理性的にも同意できる状態” を指しています。
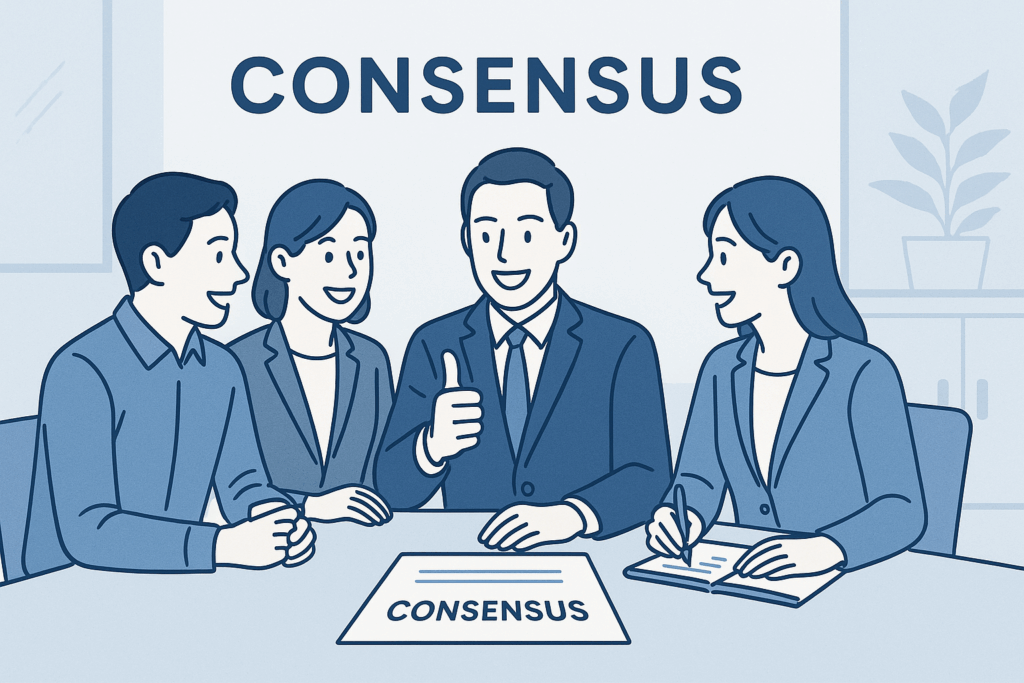
🔹 たとえばこんなケース
あるチームが「新商品の発売日」を決める会議をしているとします。
営業チームは「早く出したい」、開発チームは「品質チェックにもう少し時間が必要」と意見が割れています。
このとき、リーダーが「じゃあ、多数決で決めよう」としても、反対側には不満が残り、後々の協力体制に影響が出るかもしれません。
一方、コンセンサスを重視する会議では、双方の意見を丁寧にすり合わせます。
「早期発売のメリット」と「品質確保のリスク」を整理し、全員が納得できる妥協点――たとえば「品質確認を効率化し、1週間後に発売」――という合意に導く。
これが、真の意味での“コンセンサス”です。
🔹 多数決との違い
多数決は「数の力で決める方法」、コンセンサスは「全員が納得して決める方法」です。
つまり、効率よりも納得感を重視します。
もちろん、すべての会議でコンセンサスをとる必要はありません。
スピードが求められる場面では多数決も有効です。
しかし、長期的に協力し合うチームや、意見の衝突が多いプロジェクトほど、コンセンサス型の意思決定が力を発揮します。
🔹 コンセンサスを築く3つのコツ
- 全員の意見を出し切る場をつくる
沈黙している人の意見も引き出す。発言しづらい雰囲気をなくすことが大切です。 - 「誰が正しいか」ではなく「何が最善か」で考える
人を否定せず、アイデアの良し悪しにフォーカスします。 - 最終的な落としどころを明文化する
「こう決まった」という合意内容を議事録などで共有し、誤解を防ぎます。
これらを意識することで、チームの信頼関係が深まり、決定後の実行力も高まります。
🔹 現場での使われ方
ビジネス現場では、次のように使われます。
「この方針でコンセンサス取れてますか?」
「関係部署とコンセンサスをとってから進めてください。」
つまり、コンセンサスとは単なる“同意”ではなく、“チームとして同じ方向を向くための確認作業”なのです。
プロジェクトを前に進めるための「合意形成の技術」といえます。
🔹 まとめ
コンセンサスとは、「全員が納得して前に進むための合意」。
多数決ではなく、意見のすり合わせと共感によって築かれる信頼のプロセスです。
相手を説得するよりも、「一緒に考え、共に決める」姿勢を大切に。
コンセンサスを取れる人は、チームに安心感と一体感をもたらします。
それこそが、リーダーに求められる“本当の調整力”なのです。
📚 出典
- 経済産業省「組織内コミュニケーション向上のための合意形成手法」
- 日本能率協会『チームの力を引き出すコンセンサス・ビルディング』
- Harvard Business Review “The Art of Building Consensus in Teams”