80年代歌謡曲について
Day7:ニューミュージックの浸透 ― シティポップとの接点
1980年代の日本音楽シーンを語るうえで、「ニューミュージック」という言葉は欠かせません。1970年代後半から登場したこのジャンルは、フォークの流れを汲みながらも、より個人的で都会的な感性を重視した音楽スタイルでした。アーティスト自身が作詞・作曲を手がけ、自分の想いや生活感を率直に表現する点が大きな特徴です。井上陽水や中島みゆき、オフコースといったアーティストが先駆者として人気を集め、80年代に入ると安全地帯や佐野元春、さらにはシティポップの旗手たちとも接点を持ちながら、日本の音楽シーンを大きく変えていきました。
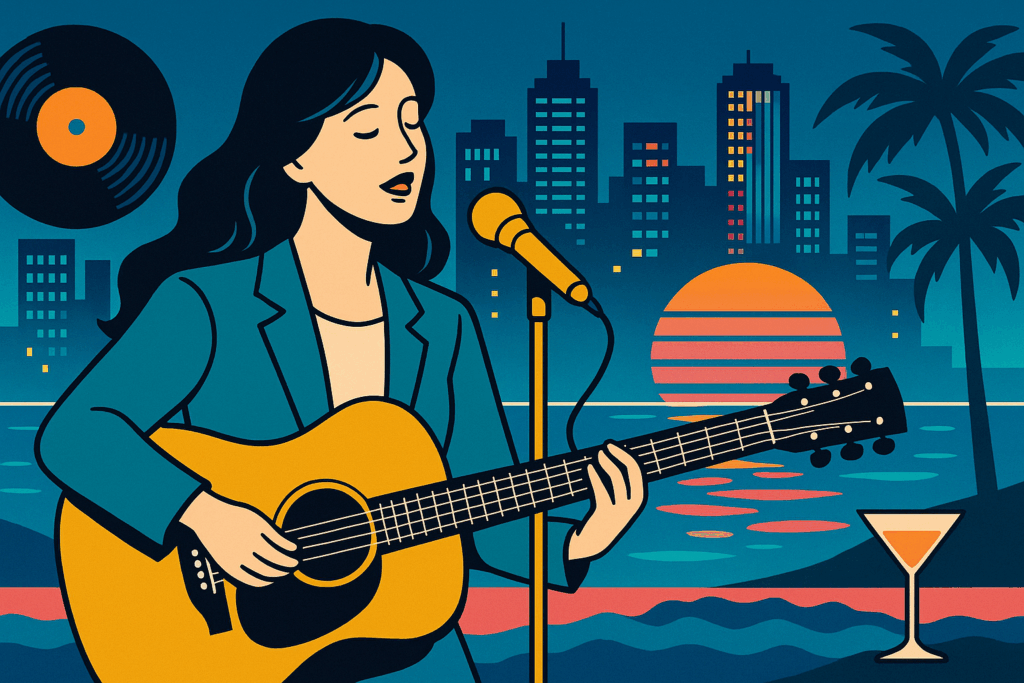
ニューミュージックの台頭とその魅力
ニューミュージックは、従来の歌謡曲や演歌とは異なり、「等身大の言葉」を大切にしました。恋愛や失恋、人生の迷いといったテーマを、自らの言葉で歌うスタイルは、特に都市で暮らす若者たちの心を強く捉えました。松任谷由実(旧名・荒井由実)の「卒業写真」やオフコースの「さよなら」といった楽曲は、歌謡曲の華やかさとは違う、しっとりとした共感を呼び起こしました。
80年代に入ると、このニューミュージックの潮流はますます一般化し、歌謡曲との境界が薄れていきます。例えば安全地帯の玉置浩二は歌謡曲の舞台にも登場しましたし、中島みゆきの楽曲はアイドルや演歌歌手にも数多くカバーされました。つまり、ニューミュージックは「シンガーソングライターの個人的な音楽」という枠を越え、日本のポピュラーミュージック全体を底上げする存在になったのです。
シティポップとの交差
1980年代を象徴するもうひとつのキーワードが「シティポップ」です。これはニューミュージックと同時代に発展し、都会的で洗練されたサウンドを特徴としました。大滝詠一の『A LONG VACATION』(1981年)や山下達郎の「クリスマス・イブ」(1983年)は、その代表格として知られています。
ニューミュージックが個人の心情や生活をリアルに描いたのに対し、シティポップは都会の夜景やリゾートの空気感を音楽に昇華しました。しかし両者は決して対立するものではなく、多くのアーティストがその境界線を自由に行き来しました。佐野元春はロック的なニューミュージックを展開しつつ、都会的な空気を取り込みましたし、竹内まりやの「プラスティック・ラブ」(1984年)は、ニューミュージック的な等身大の心情とシティポップ的なサウンドの両面を兼ね備えています。
歌謡曲への影響
このようなニューミュージックとシティポップの台頭は、歌謡曲に大きな影響を与えました。松田聖子や中森明菜といったアイドルの楽曲には、松本隆や呉田軽穂(松任谷由実)による詞曲が提供され、ニューミュージックの詩情とシティポップのアレンジが融合しました。「赤いスイートピー」や「飾りじゃないのよ涙は」といった名曲は、その典型例です。
また、歌謡曲は従来の「誰にでもわかりやすい大衆音楽」という枠を保ちながらも、ニューミュージックの個人的な表現力を取り込み、より深みのある内容へと変化しました。この融合によって、80年代の歌謡曲は「軽やかさ」と「奥行き」の両方を持ち合わせることに成功したのです。
時代背景とリスナーのニーズ
ニューミュージックとシティポップが支持を得た背景には、都市化とライフスタイルの変化がありました。80年代の日本はバブル景気に向けて急速に豊かになり、若者たちは都会的で洗練された生活に憧れを抱きました。その一方で、競争社会や人間関係の複雑さの中で、自分自身の感情を重ね合わせられる音楽を求めてもいました。
ニューミュージックは「心に寄り添う音楽」として、シティポップは「憧れを映す音楽」として、その二つを同時に満たしたのです。そして歌謡曲は、それらの要素を柔軟に取り込みながら進化していきました。
海外での再評価
興味深いのは、21世紀に入ってからのシティポップの再評価です。竹内まりやや山下達郎、大滝詠一といったアーティストの楽曲は、YouTubeやSpotifyを通じて海外でも人気を集め、特にアジアや欧米の若者に新鮮に響いています。ニューミュージック的な「心情のリアリティ」と、シティポップ的な「洗練されたサウンド」は、国境や時代を越えて共感を呼ぶ普遍性を持っていたのです。
まとめ
80年代におけるニューミュージックの浸透は、歌謡曲の在り方を大きく変えました。それは単なるジャンルの拡張ではなく、「音楽が人々の心情とライフスタイルをどのように映し出すか」という問いへの新しい答えだったといえるでしょう。
ニューミュージックは等身大の言葉を、シティポップは都会的な空気を、そして歌謡曲は大衆性を。それぞれの要素が重なり合ったことで、80年代の日本音楽はかつてないほど多層的で豊かな文化を形作ったのです。
参考文献
- 田家秀樹『ヒットの正体 80年代歌謡曲の真実』講談社、2015年
- 馬飼野元宏『シティポップとは何か』文藝春秋、2019年
- 小川真一『ニューミュージックの時代』ミュージック・マガジン、2012年
- 『朝日新聞』文化欄「ニューミュージックとシティポップの交差点」、2018年記事

