最初は謎だよね!よく聞くビジネス用語
Day8:スキーム ― 仕組みをデザインする発想
「スキーム(Scheme)」という言葉を会議や資料でよく聞くけれど、正直「仕組みってこと?」と曖昧なまま使っている人も多いのではないでしょうか。
実際、スキームという言葉は幅広い意味で使われますが、本質はシンプルです。
スキームとは、目的を達成するための仕組み・枠組み・流れを体系化したものです。
英語の “scheme” には「構想」「計画」「制度」といった意味があり、ビジネスでは「目標に向けた実行プロセス」全体を指します。
たとえば、「新商品販売スキーム」「教育スキーム」「補助金スキーム」など、特定の目的を実現するための“仕組みの設計図”として使われます。
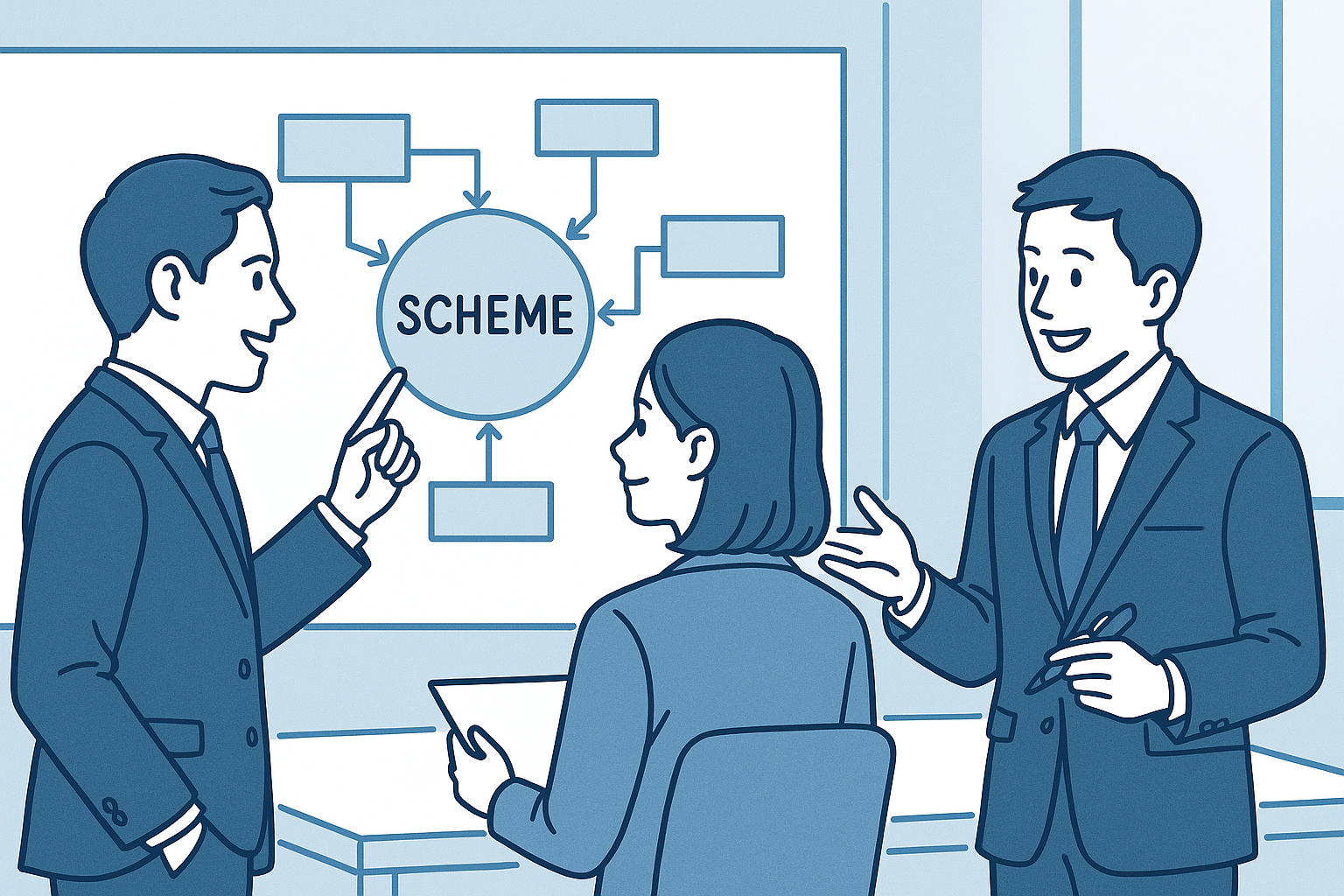
🔹 たとえばこんな例
ある企業が「自社商品の販路を拡大したい」と考えたとします。
そのためのスキームを設計するとは、以下のように“仕組み”を整理することを意味します。
- 目的:全国的に販売網を広げる
- 構成要素:販売代理店制度、オンライン販売、販促キャンペーン
- 関係者の役割:本社=戦略設計、代理店=営業、マーケ部=広告運用
- 収益構造:販売手数料・広告費・利益配分の設定
これらを明確にして「どんな流れで動くか」を描いたものがスキームです。
つまり、スキームとは「成功までの仕組みを見える化した設計図」といえます。
🔹 スキームを作るメリット
スキームがあることで、以下のようなメリットが生まれます。
- チーム全体で同じ方向を向ける
誰がどの役割を担うかが明確になり、混乱が減る。 - 課題を早期に発見できる
プロセスが見えることで、ボトルネックを特定しやすい。 - 再現性が高まる
成功した仕組みを別プロジェクトに応用できる。
「とりあえずやってみる」よりも、「どうすれば成果が出るか」を設計してから動く――それがスキーム思考の強みです。
🔹 よくある誤解
「スキーム=計画」と誤解されがちですが、両者には違いがあります。
**計画(プラン)**は「やる内容」そのものを示し、
スキームは「それを支える仕組みや流れ」を指します。
たとえば、「営業計画」は“どの地域に・何を・いつ売るか”という内容ですが、
「営業スキーム」は“どういう流れ・役割・制度でそれを実現するか”を考えることです。
🔹 現場での使われ方
ビジネス現場では、次のような言い回しが一般的です。
「このプロジェクトのスキームを整理しましょう。」
「新しい取引スキームを構築中です。」
また、行政や金融業界でも頻繁に使われます。
たとえば「地域活性化スキーム」や「投資スキーム」など、複数の組織や仕組みが連動する場合に特に使われる言葉です。
🔹 まとめ
スキームとは、目標達成に向けて仕組みを設計する思考法。
個人での仕事でも「作業の流れを仕組み化」することで、効率と再現性が格段に上がります。
大切なのは、“うまくいった流れを再現できるようにする”こと。
一度きりの成功ではなく、誰でも使える「仕組み」を作る――それがスキームを設計するビジネスパーソンの発想です。
📚 出典
- 経済産業省「事業スキーム構築のガイドライン」
- 日本能率協会『仕組みで成果を出すスキームデザイン』
- Harvard Business Review “Building Effective Business Schemes”
